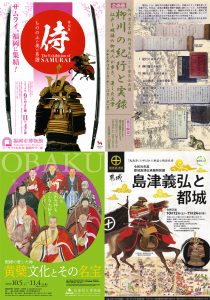2019/11/27
夏の記憶がありません。
はっと気がついたら、寒い季節に突入していました。
記憶はありませんが記録はありましたので
今年の夏と秋を駆け足で振り返ります。
まずは前回のブログで参加者特典だけ紹介した
立花家史料館友の会・公益財団法人立花財団賛助会 会員特典イベント
「旧柳川藩主・立花家のお盆」を特別体験
イベントの内容は次のようなものでした。
立花家の菩提寺である福厳寺に響く独特な黄檗宗のお経

立花家歴代のお墓参り


立花氏庭園に戻り、普段は非公開である立花家の御仏間でお参り

総位牌もご覧いただきました。

そして歴代藩主レクチャー

さらに立花家17代の兄弟3人を囲んだ夕食会

最後は燃えさかる精霊船を花火と共にお見送り


盛りだくさんな夏の午後でした。
夏から秋にかけての展覧会シーズンには
当館からの資料貸出ラッシュもありました。
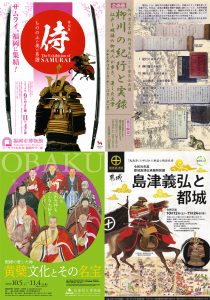
これらの他に「博物館 明治村」も
展覧会シーズンが落ち着いた現在は、返却ラッシュのまっただ中です。
9月のとある雨の日。
史料館の外に突如大量のカエルが現れピョンコピョンコと大騒ぎ。
主に騒いだのは人間の方でしたが。
翌日には影も形もなくなっていた、あのカエルたちは
いったいどこから現れ、そしてどこに去っていったのか。
まあ大方は史料館横の堀でしょうけれども。
10月17日は誾千代の命日。
この日にあわせてYouTubeの立花家史料館公式チャンネルで
「誾千代ってどんな人」を公開しました。
肖像画や文書などの資料と、これまでに撮りだめていた写真を駆使した動画です。
ラストは神々しくしてみました。
できればこれからもこのような動画を増やしていきたいと思っていますので
みなさまチャンネル登録をぜひともお願いします。
10月22日、即位礼正殿の儀の様子を見ていた学芸員が
「この風景見たことある」と、突然のデジャヴ発言。
平成のときのことを言ってるのかと思ったら
いやいや、うちの資料の中で見たと。
収蔵品のデータベースを検索してみたところ
大正天皇の御大典図がありました。

これは確かにデジャヴを感じる光景。
数千点ある資料の中の一枚(しかもこれまで展示したことはない)を
よくぞ覚えていたもんだと
早速収蔵庫から出してきて、アップで撮影し、twitterに投稿しました。
10月26日には第5回九州大名家資料研究会を
侍展開催中(当時)の福岡市博物館で開催しました。

過去の研究会の様子はこことこことをご覧ください。
今年は「実戦期の伝来資料 -勝利への願い」をテーマに
4件の報告がありました
・細川忠興所用黒糸威二枚胴具足のレプリカ製作について
・柳川藩主立花家伝来の軍書と武具-軍書の仕様どおりに作られた武具類-
・戦国武将毛利元就の軍略と祈り-毛利家伝来資料から見た-
・実戦期における甲冑の様式変遷
九州のみならず中国四国地方の研究者も参加され
とても有意義な会になりました。
(その後の懇親会も含めて)
木の葉を散らす冷たい風が吹き、松濤園では鴨が群れ遊ぶ季節となりました。
世間は年末に近付きつつありますが、立花財団は12月から新年度となります。
次年度の展示スケジュールはこちらでご覧ください。
刀剣展がいつもとちょっとだけ違うことになりそうです。
「記録って大事だな」とは
歴史でご飯を食べている身として常々思っていましたが
今回改めてひしひしと感じたことでした。
これからは記憶喪失に気を付けます。
タグ: 九州大名家, 九州大名家資料研究会, 史料館Twitter, 立花家のお盆, 誾千代, 講座・講演会
Posted in 日々折々 | 記録頼みで振り返る夏と秋の出来事 はコメントを受け付けていません
▲ページの先頭へ
2014/11/26
11月22日(土)。
立花財団が事務局を務める「九州大名家資料研究会」が
柳川古文書館に於いて開催されました。
この研究会は、大名家のいとなみ全般に関わる伝来資料である「大名家資料」
-文書、典籍、大名道具、建築物、庭園、発掘資料など-の研究を
従来の研究区分を超えて横断的に進め
その成果が博物館でのより充実した学芸活動への支援となることや
研究者・学芸員のネットワーク作りや情報交換の場となることなどを
目的としたものです。
第1回は「大名家資料の収蔵と公開の現況」をテーマとし
今年の3月29日に開催しました。
そして第2回となる今回のテーマは
「大名家資料としての古文書
-伝来・保管・編纂そして現代アーカイブ形成-」

報告は
福岡市博物館 堀本一繁氏
「御感書」成巻にみる黒田家の家格意識について
柳川古文書館 田渕義樹氏
立花家文書の整理と管理
長野市立博物館 原田和彦氏
松代藩・真田家における「家」意識と文書の整理・管理
北九州市立小倉城庭園 立畠敦子氏
近世武家礼法伝書の紹介
-北九州市立小倉城庭園 寄託 小笠原礼法伝書 五十三巻の場合-

大名家では、どのような文書を、どのような状態で保管していたのか。
またそれにはどのような意義があり、どのようにして現在のまとまりに至ったのか。
共に保管されていた道具類との関係は。
参勤交代のときにはどうしていたのか。
などなど、大名家資料としての文書に関する報告がされました。
さらにその後の質疑応答(フリートーク)では
典籍類の扱いや、各大名家に伝わる藩主の肖像画等が話題となりました。

活発な議論を終えた後は、柳川藩主立花邸 御花の料亭に場所を移して懇親会。

会場は新鈴の間。
15代当主・立花鑑徳の居間だった部屋です。
乾杯はせっかくなので2日前に解禁となったボジョレー・ヌーヴォーで。

初めましての方には自己紹介を
お久しぶりの方には近況報告を
頻繁に会う方とは普段どおりに
楽しい話とおいしい料理を堪能しました。
広大な分野に及ぶ大名家資料ですので
今後も多様なテーマでの開催となるでしょう。
立花財団は事務局として、充実した学芸活動を支援していきます。
タグ: 九州大名家, 九州大名家資料研究会
Posted in 立花財団からのお知らせ | 大名家資料としての古文書 はコメントを受け付けていません
▲ページの先頭へ
2014/4/3
新年度を迎え、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
立花財団は、事業年度が12月始まりですので、いつも通りの月末・月初でした。
とはいえ、いつもと違う初めてのことも実はありました。
時は3月29日(土)。
場所は柳川古文書館。
第1回「九州大名家資料研究会」開催。
わが立花財団では、活動の目的のひとつとして
九州地区の大名家資料研究への支援と連携を掲げています。
そうして、この研究会の事務局を務める運びとなりました。
一言で「大名家資料」といっても、その分野は広大なものです。
文書、典籍、大名道具(いわゆる美術工芸品が主となる)、建築物、庭園、発掘資料などなど。
大名家資料を収蔵する施設の学芸員や、大学などの近世史料の研究者にとっては
従来の研究区分を超えて、横断的に研究を深めていくことが必要です。
各々の資料を大名家資料の中に位置づけし、史料批判を加えながら研究を進め
その成果が、博物館でのより充実した学芸活動への支援となること。
もちろん、この研究会の場が、九州各地域にある大名家資料収蔵館の
学芸員のネットワーク作りの助けとなったり、
大学などに所属する研究者と、実際に資料を所蔵している施設の学芸員との
情報交換の場になったりすること。
そういったことが、本研究会の主旨となっています。
記念すべき第1回のテーマは「大名家資料の収蔵と公開の現況」。
九州各地と山口県から、26名の学芸員・研究者が参加しました。

報告は
それぞれの家に関する資料を収蔵管理している施設。
資料の所蔵者と収蔵管理施設の関係。
資料の目録の形態や公開状況、公開条件。
資料の調査や借用への対応や利用条件。
といった内容を
鍋島家、毛利家、細川家、立花家の資料収蔵館が行いました。
研究会後は、近隣のお店で懇親会です。

ここ「北斗星」は、三柱神社の参道脇にあります。
ちょうどこの日は流鏑馬の前日でした。

雨の中、馬場の整備中。
結構な雨で周囲も水浸しでしたが
翌日には雨も止み、無事に開催されたようです。

雨に煙る柳川の町と満開の桜の景色が一望できる、素敵なロケーション。

「立花財団 御一同様(予約名)」は、中華料理を楽しみながら親睦を深めたのでした。
博物館協議会などで他の美術館・博物館と交流する機会はありますが
「大名家資料」を扱う館同士だと
同じような問題を抱えていたり、同じような感覚を持っていたりして
他にはない連帯感があります。
また今回、大名家資料収蔵館関係者には
甲冑などの資料を「うちの子」と呼んで、愛着を持っている人が割と多いことがわかりました。
(立花家史料館スタッフ調べ)
これから年に数回の会を開催しながら、活発な研究会にしていきたいと考えています。
そしてその成果を、展示などを通してみなさんにお伝えできればと思っています。
タグ: 九州大名家, 九州大名家資料研究会
Posted in 立花財団からのお知らせ | 「九州大名家資料研究会」始動 はコメントを受け付けていません
▲ページの先頭へ