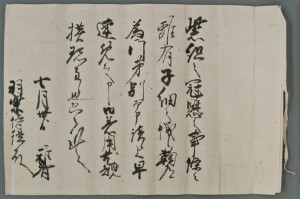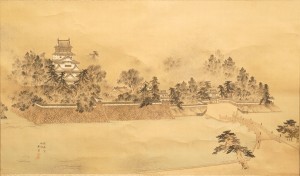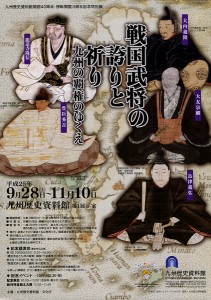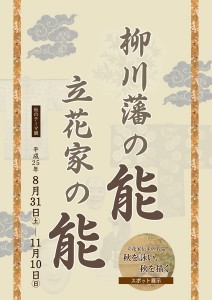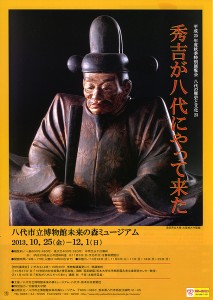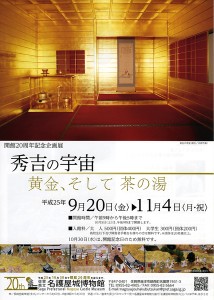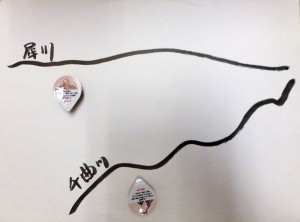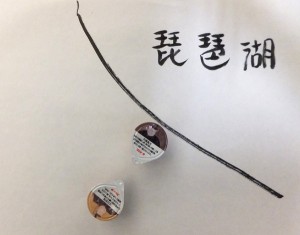戦国武将ライダー
2013/11/29この10月から始まった、新しい仮面ライダーシリーズ「仮面ライダー鎧武(ガイム)」。
ご覧になったでしょうか。
戦国武将とフルーツがモチーフとなった、斬新なデザインのライダーです。
主人公の兜は明らかに東北の独眼竜がモチーフと思われます。
そしてフルーツは、オレンジ、バナナ、メロン、ブドウ、そしてドリアンなどなど。
それらが頭上から降ってくる変身シーンは必見です。
特にバナナが。
お子様に大人気の仮面ライダーに、戦国武将の甲冑が採用されたことから
もしや子どもたちの間で甲冑人気が巻き起こるのでは(錠前の方が人気ありそうだけど)。
そんな淡い期待を胸に、天下の仮面ライダーに便乗するべく
立花家史料館でも新しい戦国武将ライダーを考案してみました。
仮面ライダーソーモ
[あらすじ]
高橋家の長男である主人公は、父の同僚である戸次家の養子となる。
立派な青年に成長し戦乱の世に身を投じた主人公は
ひょんなことから仮面ライダーソーモに変身してしまう。
二人の父を失いながらも、ソーモとして活躍を続ける主人公。
やがて権力者に認められ、大きな町を統治する立場となったが
天下分け目のライダー合戦に負け、町を追われてしまう。
流浪の日々を送る主人公に、果たして明るい未来はくるのか。
回を追うごとに主人公の名前が変わっていくところも、見どころのひとつ。
[名前の由来]
「ソーモ」の名は、主人公の最後の名前「立斎宗茂(りっさいそうも)」から付けられた。
[鎧と兜]
「ムーンリングアームズ」
主人公が「統虎」「宗虎」「正成」と名乗っていた頃の装備。
月の輪を表した胸の赤いリングは、友達の加藤君のと似てる。
「ブッダボディアームズ」
主人公が「親成」「政高」「尚政」と名乗っていた頃の装備。
ソーモはブッダボディアームズに変身して、天下分け目のライダー合戦を戦ったが
味方側が負け、町を追い出されることになった。
[武器]
「ナガミツソード」
主人公が養子として戸次家に行くときに
お父さんのジョーウンからもらったもの。
いつも大切に持っている。
「雷切丸」
もとは戸次のお父さん・ドーセツのものだった。
このソードで斬られた雷神が、ときどきリベンジしにやってきて
ちょっと面倒くさい。
「スミナワ砲」
ご近所の黒田君とちょっとした勝負をしたときの戦利品。
玉がとても真っ直ぐ飛ぶので、この名前がついた。
[脚力]
主人公は脚力があり、キックの精度も高い。
爆弾マリを使って敵を倒すこともできる。
[乗り物]
「ギョーヨーサドル」
これを馬に乗せると、馬の性能が格段にアップする。
友達の加藤君にもらった。
「ブラックロッド」
ギョーヨーサドルによって格段に性能が上がった馬が
さらに早く走る。
これは加藤君からもらったものではない。
[指揮具]
「クロワッサン扇」
共に戦う仲間を鼓舞するのに使う、 おしゃれなデザインの扇。
「マンダラ扇」
共に戦う仲間を鼓舞するのに使う、宗教的なデザインの扇。
秘密の書物に書かれている通りに作った自信作。
[憩いのひとときの道具]
「笛」
ときには戦いに明け暮れる日々に疲れるときもある。
そんなときには笛を吹くと、心が穏やかになる。
[ガレージ]
大きな町を統治していた頃、主人公が本拠地としていた「城」。
流浪の日々を送っていた主人公は、20年ぶりにこの「城」に戻ってくることとなる。