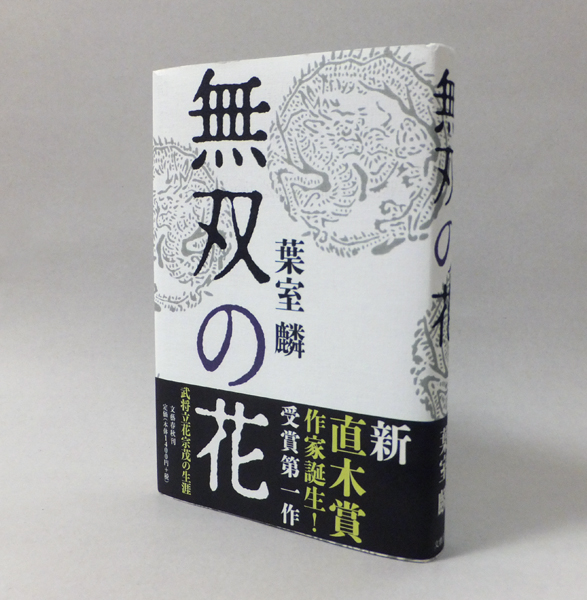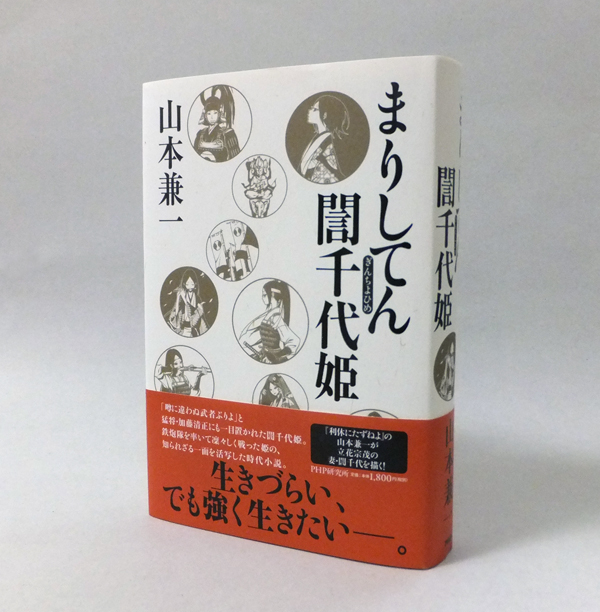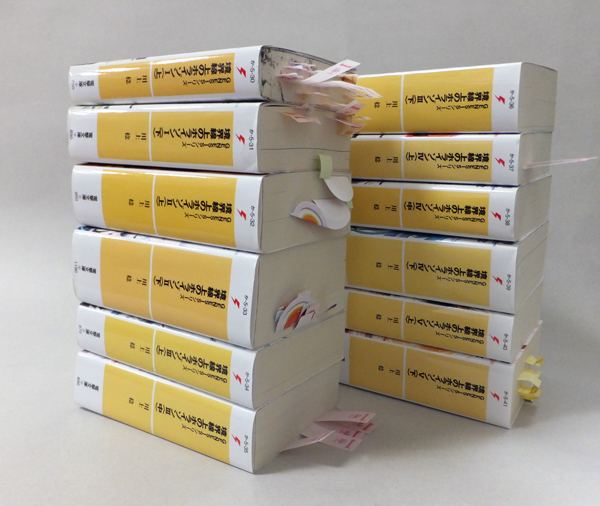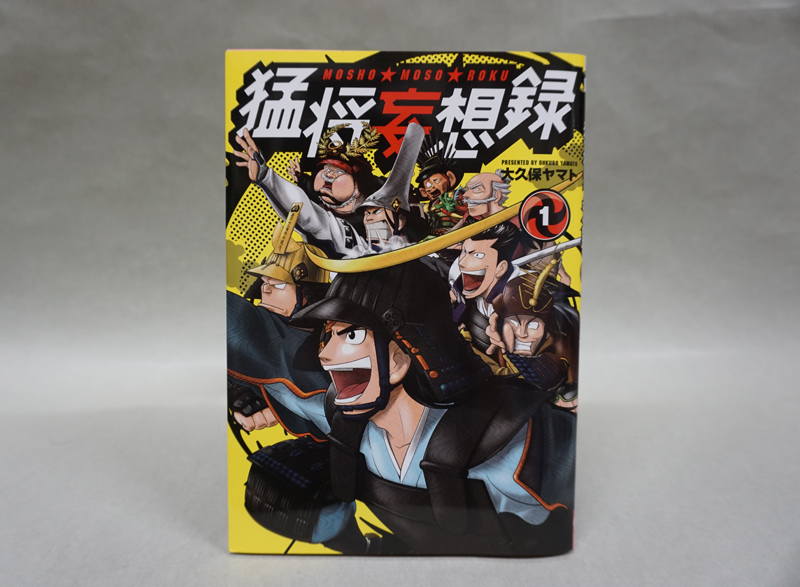先日、吉川史料館 🔗 (山口県岩国市横町)にて、吉川広家公没後400年記念/開館30周年記念展 第二期「広家と秀吉」【2025.9.6~11.30】を拝見しました。
吉川史料館 🔗 の 公式X(旧Twitter)より
同世代くらいだろうと思っていましたが、確かめると吉川広家[1561–1625]は立花宗茂[1567–1642]より6歳年上。広家公没後400年と聞いてソワソワしましたが、宗茂さんの場合は2042年なので、まだまだ焦らずともよさそうです。
毎度の言い訳となりますが、わたしは美術史を専門とする学芸員なので、立花家を中心とする九州の戦国事情については少々頭に入れていますが、ヨソの戦国事情まではなかなか手が回っておりません。
いろいろとご縁もあって、毛利家や吉川家に関する展示や史跡を訪ねる機会は少なくないのですが、どうにもボンヤリとしか把握できておらず、お恥ずかしい限りです。
それでも、だいたい同世代の宗茂さんと広家さんは、その人生に起きる大事件にも共通点が多く、大変勉強になりました。
そして、吉川史料館の最後のコーナー「鳥取岩国姉妹都市縁組30周年記念」にて、『吉川経家書状 天正9年10月25日付』(石見吉川家文書140)〚重要文化財 吉川家文書〛に出会ってしまいました。
平仮名が多く、柔らかな印象を感じる小ぶりの手紙。
キャプションには「切腹をした当日に子ども達に宛てた遺書」的な説明が……
え、遺書? 切腹?鳥取城の攻防?
経家さんに何があったの?
ともに展示されていた、父親の吉川経安に宛てた遺書 『吉川経家自筆書状』(石見吉川家文書137) 〚重要文化財 吉川家文書〛は漢字でスラスラと書かれているので、子ども宛の遺書の特別さが際立ちます。
宛名に並ぶ子ども達の幼名「あちやこ/かめしゆ/かめ五/とく五」の文字が胸に迫りました。
吉川経家さんに何があったのか、”鳥取城の攻防”については後ほど落ち着いて調べてみようと思いつつ、後ろ髪を引かれながら吉川史料館を後にしました。
しかし、岩国の皆さまは周到に企画されていたのです。
続いてお隣の、岩国市立博物館 岩国徴古館 🔗 (山口県岩国市横町)にて、岩国市・鳥取市 姉妹都市提携30周年記念/吉川広家没後400年「吉川広家・経家の生きた時代」【2025.10.5~12.4】を拝見しました。
わたしが知りたかったことは展示室の「四、落城」にすべて書いてありました。
岩国市立博物館 岩国徴古館 🔗 の公式Facebook より
岩国徴古館が作成されたパンフレット「吉川経家と鳥取城の攻防」の年表を参考にすると、
天正8年(1580)
5月 羽柴(豊臣)秀長の攻撃により山名佑豊が羽柴秀吉に降伏
毛利方は但馬の勢力を失う
6月 鳥取城が落城、山名豊国が降伏
9月 山名豊国が家臣の中村春続、森下道誉らによって追放
天正9年(1581)
3月 吉川経家が鳥取城に入る
7月 羽柴(豊臣)秀吉が鳥取城を包囲
10月 鳥取城が落城、吉川経家【享年35】が自刃
――という経緯が示されていました。
ああ……中国地方に、豊臣兄弟!がやってきていたのか……
“鳥取城の攻防”について詳しく知りたい方は、ぜひ岩国市立博物館 岩国徴古館 🔗 ・ 吉川史料館 🔗 へ。まだ展覧会の会期に間に合います。
豊臣兄弟!は九州へもやってきます。
天正13年(1585)
10月 豊臣秀吉、島津義久に大友義統との和睦を命じる
天正14年(1586)
6月 島津義久、九州平定をめざして大軍を北上させる
7月 高橋紹運、島津軍に岩屋城にて抗戦の後、敗死【享年39】
8月 島津軍、宝満城を落とし、宗茂の母と弟を捕虜に。
島津軍、立花山城を包囲するも、豊臣の援軍が来ること等を告げられ退く
9月 立花宗茂、 島津方の高鳥居城を激戦の末に攻略
後に秀吉から”九州之一物”と激賞される
10月 秀吉の先遣として毛利輝元・吉川広家・小早川隆景らの中国勢が九州に入る
天正15年(1587)
3月 豊臣秀吉、島津氏攻めのため九州に入り、豊前(福岡県)の攻略に進む
秀吉、豊臣秀長に豊日路(大分・宮崎方面)の南下を命じる
――かなり端折った、ざっくりまとめた年表ですが、今回はこのあたりまで。
豊臣兄弟!がやってきたがために戦となり、 吉川経家も高橋紹運も命を失ってしまいました。
お互いの子どもたちの運命も、豊臣兄弟!により大きく変わってしまったのです。
豊臣兄弟!と立花宗茂については、いずれ改めて語りたいところです。
もうひとつ、吉川史料館で気になった「鳥取岩国姉妹都市縁組30周年」の経緯。
この回答も岩国徴古館に用意されていました。
豊臣兄弟!がやってきた影響が後世にまで。恐るべし……。
来年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』も、とうとうやってきます。
その予習として、ぜひ山口県岩国へ。
福岡県柳川の地から、心よりオススメいたします。
参考文献
東京大学史料編纂所HP▶️ 《データベース検索▶️ 大日本史料総合データベース
中野等『人物叢書227 立花宗茂』2001初版2012.10.1第2刷 吉川弘文館、中野等・穴井綾香『柳川の歴史4近世大名 立花家』2012.3.31 柳川市
📝 学芸員がこつこつ綴っています。お暇な折にどうぞ。⤷